サックスのお手入れ方法


あどるふ
サックス吹きとして学生のころより約15年となりました。今でも音楽はいつもそばにある日常として楽しくアマチュア活動中♪音楽業界に従事。
サックスのお手入れは普段どこまでやればいいのかご存知ですか?
普段のお手入れはしっかりやってるけど、それ以外のお手入れはあまり知らないという方は多いかと思います。
今回はそんな普段のお手入れ方法から時々やってほしいお手入れまで、ぜひ知って欲しいサックスの取り扱いについてまとめています。ぜひご覧ください。
サックスパートについて
サックスにはパートで分けると基本7つに分かれます。それは
- ソプラニーノ
- ソプラノ
- アルト
- テナー
- バリトン
- バス
- コントラバス
です。その他にも亜種としてピッコロとサブコントラバスがあります。
普段目にしたり聞いたりするのはソプラノ・アルト・テナー・バリトンの4つであり、サックスアンサンブルでもこの4パートで構成されています。
今回のサックスのお手入れについてですが、お手入れ方法が同じソプラノ・アルト・テナーについてまとめていきたいと思います。
普段のお手入れ
みなさんは普段どのようにお手入れをされていますか?きっと楽器を吹いた後に水分を取って拭き上げているかと思いますが、それぞれの意味や効果・注意点はご存知でしょうか。
今回は4つの項目に分けてみましたのでご覧ください。
スワブ編
まずはなんといっても基本となるクリーニングスワブです。
サイズはヤマハのものですとアルトとテナー用に”SAX”があり
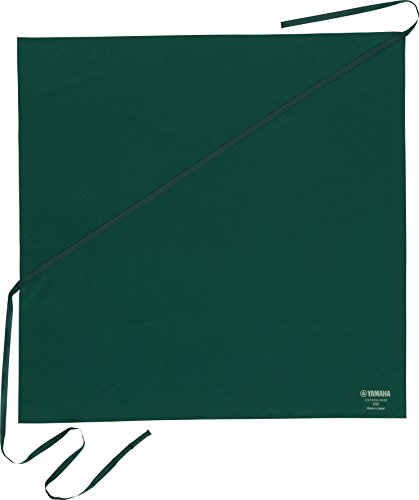 ヤマハ YAMAHA クリーニングスワブ SAX CLSSAX2
ヤマハ YAMAHA クリーニングスワブ SAX CLSSAX2
ソプラノは”ソプラノ”がありますので、それぞれのパートに適したものを準備してください。
 YAMAHA/ヤマハ ソプラノサックス用 CLSSS2
YAMAHA/ヤマハ ソプラノサックス用 CLSSS2
ネックは”S”を使用してください。
 ヤマハ YAMAHA クリーニングスワブ S CLSS2
ヤマハ YAMAHA クリーニングスワブ S CLSS2
スワブとは吸水性の高い布に紐が付いており、その紐の先端に重りが付いているものです。まずは基本的な通し方ですが、重りを先行してベルから管内に入れ、サックスの向きをうまく変えながら反対側(ネックを差し込む口)から出します。
 そしてそのまま引っ張りあげます。
そしてそのまま引っ張りあげます。
 これを2~3回繰り返します。これにより管内に残った水分を取ります。ネックも同様に通して下さい。
これを2~3回繰り返します。これにより管内に残った水分を取ります。ネックも同様に通して下さい。
これがクリーニングスワブの使用方法です。

この作業は、管内の水分をしっかり取るために必要です。水分は楽器に錆ができたり、調整の狂いが起こりやすくなったりするため、ここでしっかり内側から取り除いてください。
この際注意としては、スワブをしっかり広げることです。これはスワブが管内で詰まってしまい抜けなくなることを防ぐためです。
また、ソプラノサックスの場合引き抜くことは出来ませんので、止まるところまで通したらまたベル側から戻して下さい。
続いてクリーニングペーパーです。
ペーパー編
タンポと呼ばれるキーのカップの中に納まっているパッドの水分を取るために使用するのがクリーニングペーパーです。
 ヤマハ YAMAHA クリーニングペーパー CP3
ヤマハ YAMAHA クリーニングペーパー CP3これはタンポと音孔(おんこう)と呼ばれる管体の穴との間に挟みこむことで、タンポに吸収された水分を取るためのものです。
キーと音孔の間に挟みこみ何度かキーを開閉することで、タンポに吸収されていた水分や管体の穴のくぼみに残っている水分を取ることができます。

この作業はタンポの水分を出来る限り除去することで、タンポ自体の痛みを抑えるために行います。痛みが進むとタンポの交換という修理が必要となるのですが、この作業をしっかり行うかどうかで交換までの期間が大きく変わってきます。
この際の注意としては、ペーパーをタンポに挟み込んだまま引き抜かないことです。
これはペーパーがタンポにくっついたまま破れることを防ぐためです。水分を吸収し濡れたペーパーはどうしても破けやすいため、注意してください。
続いて仕上げの拭き上げです。
拭き上げ編
拭き上げは言葉のとおり管体の拭き掃除です。これはクロスと呼ばれる布を使用します。最近のクロスはマイクロファイバーのものが主流となってます。
 ヤマハ YAMAHA ポリシングクロス DX M PCDXM3
ヤマハ YAMAHA ポリシングクロス DX M PCDXM3このクロスを使って指が触れた場所や、汚れている場所を拭いていきます。

拭き上げは管体表面の油分や汚れを除去するために行います。この汚れなどを残すと管体表面の塗装や金属部分が痛み、それが進行すると塗装が剥げてしまったり錆びたりしてしまいます。
サックスの表面には
- ラッカー塗装
- メッキ加工
- 無垢(管体の表面に何も処理がされていないもの)
の3つの仕上げがありますが、どの仕上げでも指などの油分や水分が付着したままにしておくと痛んでいきます。その痛みを抑えるために行います。
拭き上げの注意は擦らないの一言につきます。あくまでも拭く作業なので、軽く当てて撫でるように動かして下さい。
磨くように擦っていくと磨き傷と呼ばれる細かい傷が増えていき曇ったような状態になってしまいます。
リード編
吹き終わったリードは水分を含んでいるため、まずは水分を取ります。
水分が多く残ったままではカビが生えやすい・次回の使用時に鳴りにくいからです。これはティッシュやタオルを使用する人と、指で挟んで指をスライドさせて水分で飛ばす人がいますが、このあとの水分に対するケアをしっかり行えばどちらでも問題はありません。
注意点としてティッシュやタオルを使用する場合はリードを挟んで水分を吸わせるようにしてください。リードをなぞるように動かすとリードにタオルの繊維等が引っかかり最悪割れたりします。
水分を取ったあとはできるだけリードケースに入れて乾かしてあげて下さい。リードケースに入れる理由としては、乾く過程でのリードの歪みを最小限にするためです。特にリードの先端が波打つと音への影響も大きくなります。
そのリードケースですが、リードに元々付いているものでもいいのですが、複数枚収納できるリードケースを準備いただくと管理がとても楽になります。
 D'Addario WOODWINDS (ダダリオウッドウインズ)ヴァイタライザー・リードケース マルチ(Multi)RVCASE04
D'Addario WOODWINDS (ダダリオウッドウインズ)ヴァイタライザー・リードケース マルチ(Multi)RVCASE04リードケースには湿度調整剤を使用するタイプもあり、乾きすぎず湿りすぎずの状態を維持することもできます。もし興味があれば楽器店で覗いてみて下さい。
時々やってほしいメンテナンス
いつも行う必要はないけれど、時々やってほしいメンテナンスをご紹介します。
オイルアップ
一つはキーのオイルアップです。ヤマハでいうキーオイル(H)など、キー用のオイルを月に1~2回さしてください。オイルをさす場所は、キーの継ぎ目になる部分です。
 YAMAHA / ヤマハ キーオイル へヴィー KOH3
YAMAHA / ヤマハ キーオイル へヴィー KOH3

キーが可動する時の継ぎ目に少量乗せるようにさしてキーを動作させます。
すると中に少しずつ入っていきますが、全てのオイルが入ることはないので最後は余ったオイルを拭き取って下さい。楽器のオイルが減るとキーノイズに繋がりますので、定期的にやってみて下さい。
ベタ付き
もう一つはタンポのベタつきです。タンポの表面は皮ですが、その皮の部分と音孔が張り付くことがサックスはよくあります。特に普段から閉じているキーは顕著に症状がでるかと思います。
この症状が起こったときに使用するのはパウダーペーパーなどの張り付き解消の用品です。
 ヤマハ YAMAHA パウダーペーパー PP3
ヤマハ YAMAHA パウダーペーパー PP3
パウダーペーパーの使い方ですが、まずプリントがしっかり入っている面が表、薄い面が裏になります。粉が付いているのは裏の面になります。
この粉がついた裏の面をタンポ側に向けて差込み、何度かカップを開閉します。すると張り付きの原因になる部分に粉がつき、張り付きを防止してくれます。

お手入れにおける注意事項
各作業の目的を意識して
お手入れにおける注意事項ですが、まずは各作業ごとに終えたとき目的が達成できているか確認をして下さい。
たとえば、クリーニングスワブを通したあとに水分が取れているか確認するといったことです。慣れてくるとただの作業になり、水分が取れていなくてもスワブを通したから終わりとなりがちです。あくまでも目的があってのお手入れということを忘れないで下さい。
次にお手入れ用品のお手入れです。
お手入れ用品のお手入れ
当然ながらクリーニングスワブもクロスも使えば使うほど汚れてきます。この汚れを放って置くとお手入れしているつもりがまったく効果がないということになりかねません。そのため、月に1~2回は手洗いや洗濯をしてあげて下さい。
またお手入れをした後のことになりますが、水分を吸ったスワブなどはケースとは別にすることをオススメいたします。
それはせっかくスワブで水分をとってもケースの中に入れていると、そこから水分が気化しケース内の湿度を上げてしまうからです。それではせっかくのお手入れの意味が半減してしまい、楽器も錆やすくなってしまいます。
そのためスワブは別管理をする、もしくは帰宅などの移動後にケースから出してあげて下さい。
こんな時はどうしたらいい?
サックスを日々演奏していると、どうしても不具合というものは発生します。いくつかその事例と対処方法を紹介します。
”ソ#”または”低いド#”の音が遅れて切り替わる・または切り替わらない
これはタンポの張り付きが悪化したことにより起こる症状です。
なぜこの二つなのかと言うと、キーが開く時の力がバネのみで尚且つ普段から閉じているキーだからです。普段から閉じているということはタンポが張り付きやすくなり、バネの力 < 張り付く力となった時スムーズにキーが開かなくなります。
対処方法は”ソ#”であれば”ソ”を出すときに開閉するキーの一つしたのキー(普段閉じているキーです)が、”ド#”であればベルの先から3つ目のキー(こちらも普段閉じています)がそれぞれ開きにくくなっているかと思います。そこにパウダーペーパーを使用してみて下さい。症状が解消されるはずです。

カチャカチャ金属音がする
この場合は2つの理由が考えられます。金属部分が接触しているかオイルが切れているかです。それぞれ対処方法は変わってきます。
金属部分が接触している場合は、キーが曲がっていたり、クッションとなるフェルトやコルクが剥がれている時です。これは楽器店でリペアマンに見てもらって下さい。
オイル切れは、音が発生している部分にオイルをさすと止まります。ですが場所の特定が難しかったりオイル切れ以外の要因がある場合はそれだけでは消えない場合もあるため、その場合はリペアマンに見てもらって下さい。
ネジが飛び出ている
楽器のネジは音の振動で緩むことがあります。
そのため気付くとネジが飛び出ているということがありますが、楽器のネジは締めきっても問題ないものとそうでないものがあるため判断が難しいです。
もし自分で対処をしてみる場合は一気にネジを締め込まずに少しずつ回して、キーの動作を確認しながら進めて下さい。もし上手く出来た場合でも近日中に一度リペアマンに点検をお願いする方がいいでしょう。
マウスピースが緩くチューニングが出来ない
これはネックのコルクが圧縮され細くなったため起こる症状です。
そのため、リペアマンに新しいコルクへ変えてもらいましょう。もしすぐに交換が出来ない場合は応急対策としてクリーニングペーパーを2つ折りにしたものをコルクに巻いた状態でマウスピースを差し込んでみて下さい。少しは手ごたえが戻るはずです。
いくつか症状と対処を紹介しましたが、何か不具合が生じ自分で対処できても不安が残ることもあるかと思います。そんな時は楽器のお医者さんであるリペアマンを頼ってみて下さい。
ちょっとしたことであればその場で対応してくれることもよくあります。また、特に気にならなくても定期的に点検に持っていくことで現在の状態を知ることもできます。
ぜひかかりつけの病院ならぬリペア工房を見つけておくといいと思います。
おわりに
サックスのお手入れについて紹介をしてきましたが、演奏だけではなくお手入れもしっかり行うことで普段あまりやらない人との差は広がっていきます。
今回このサックスのお手入れ方法についてここまで読んでいただけたのであれば、その点は大丈夫だと思います。
お手入れを行うということは楽器を良い状態で保つことであり楽器を大事にするということです。日々のお手入れをただの作業ととらえず愛情を持ってしっかり行ってあげて下さい。

あどるふ
サックス吹きとして学生のころより約15年となりました。今でも音楽はいつもそばにある日常として楽しくアマチュア活動中♪音楽業界に従事。


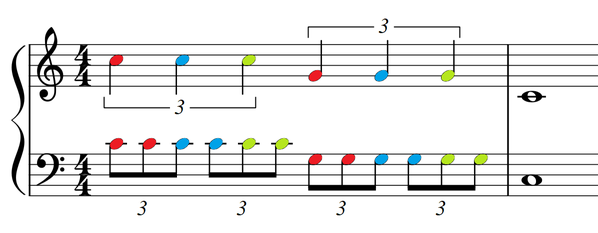



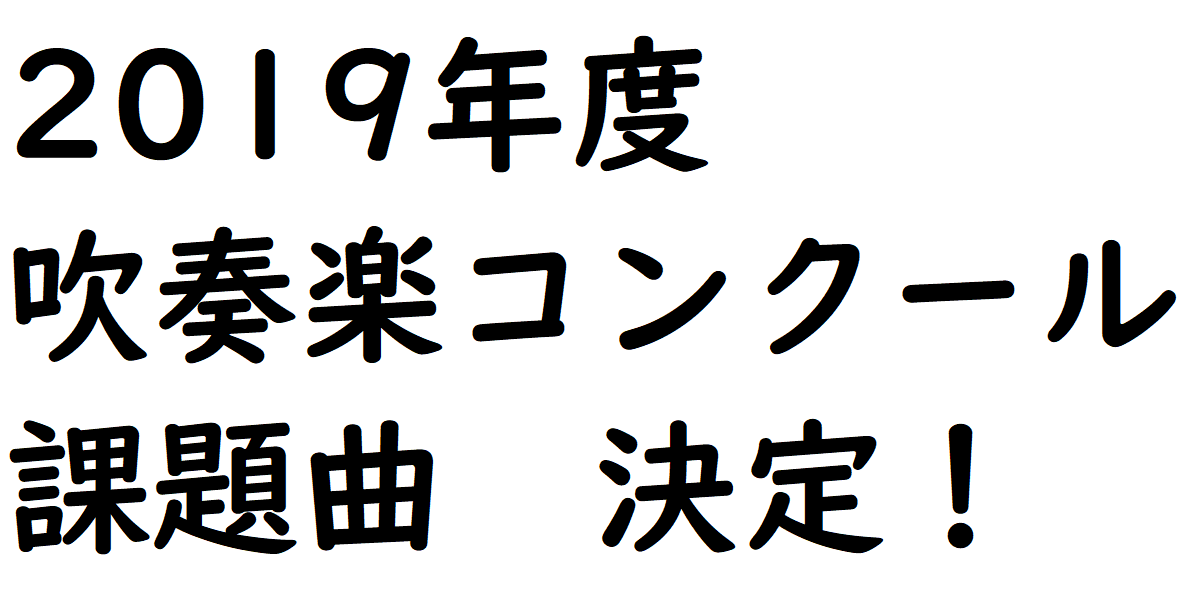







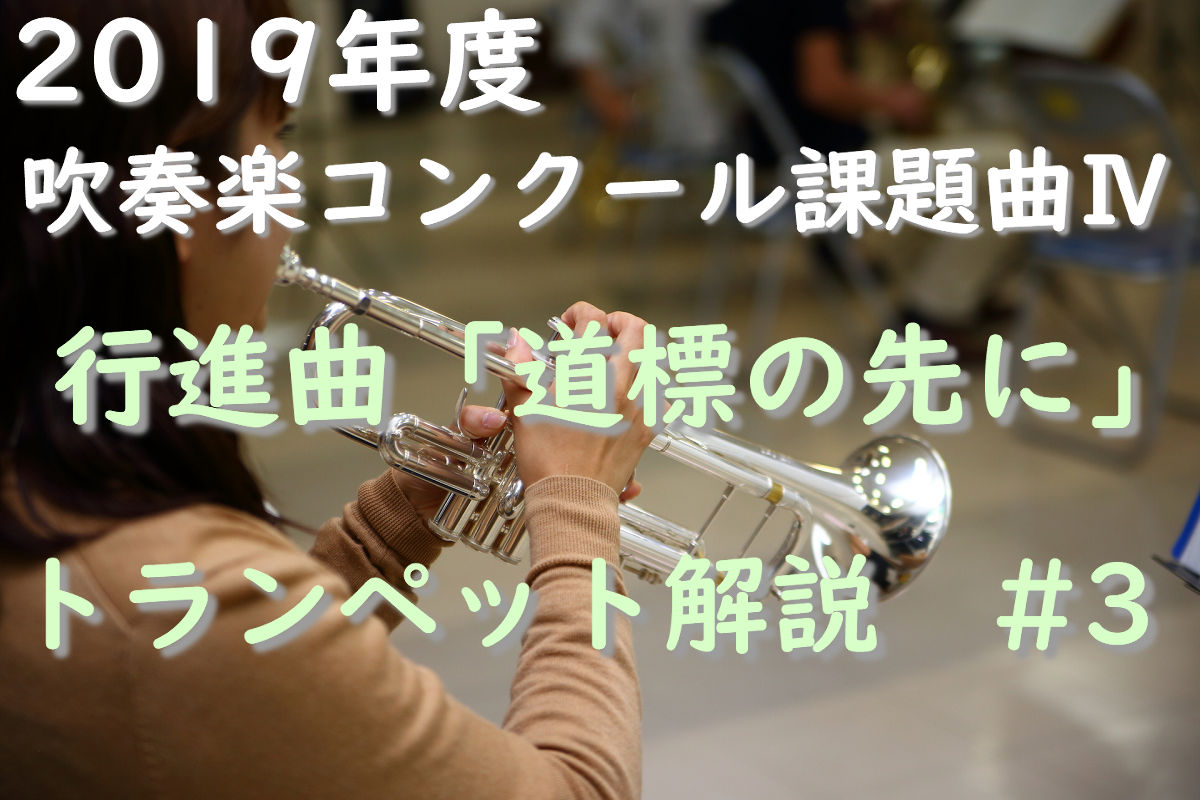
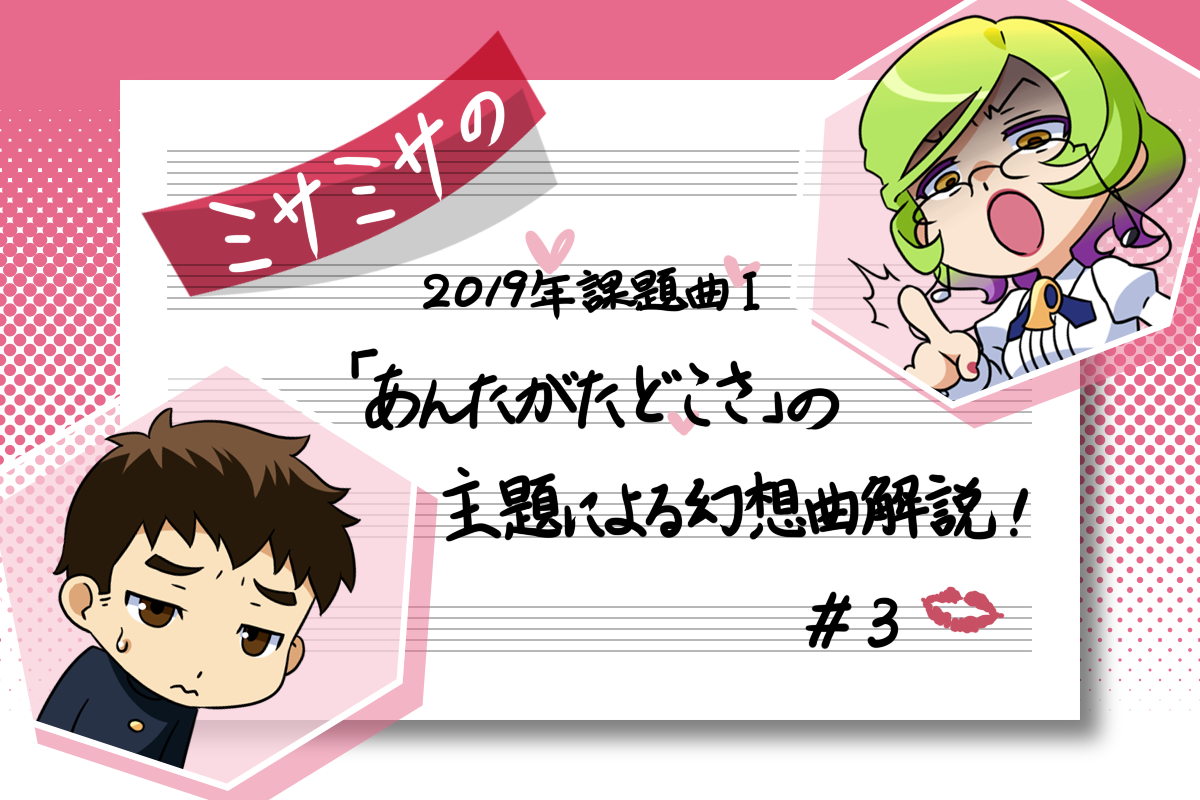
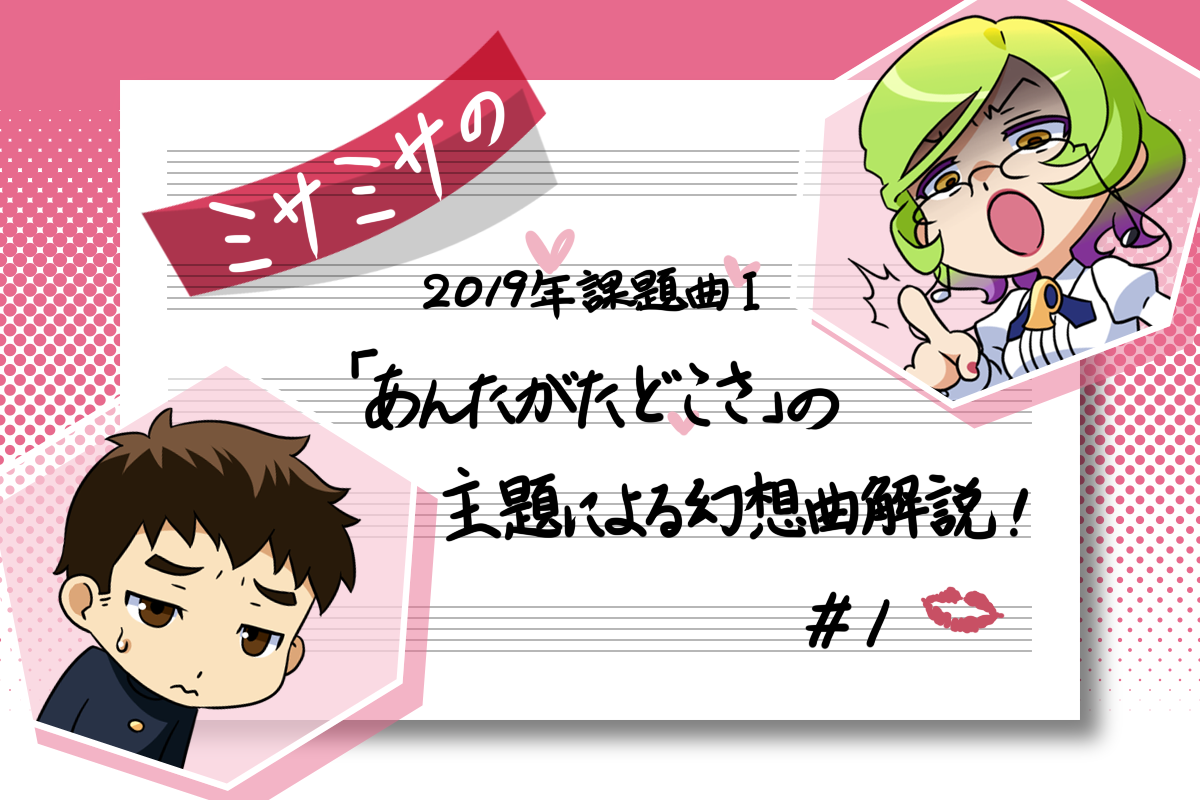


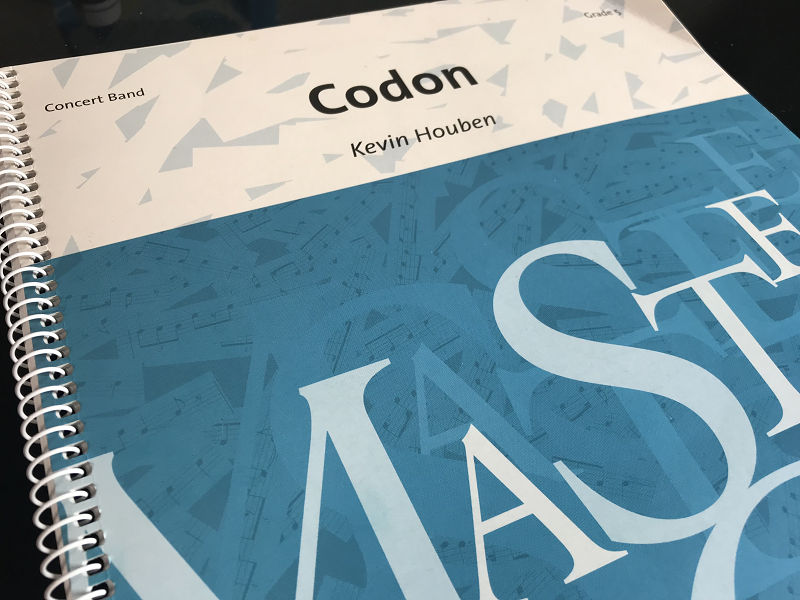
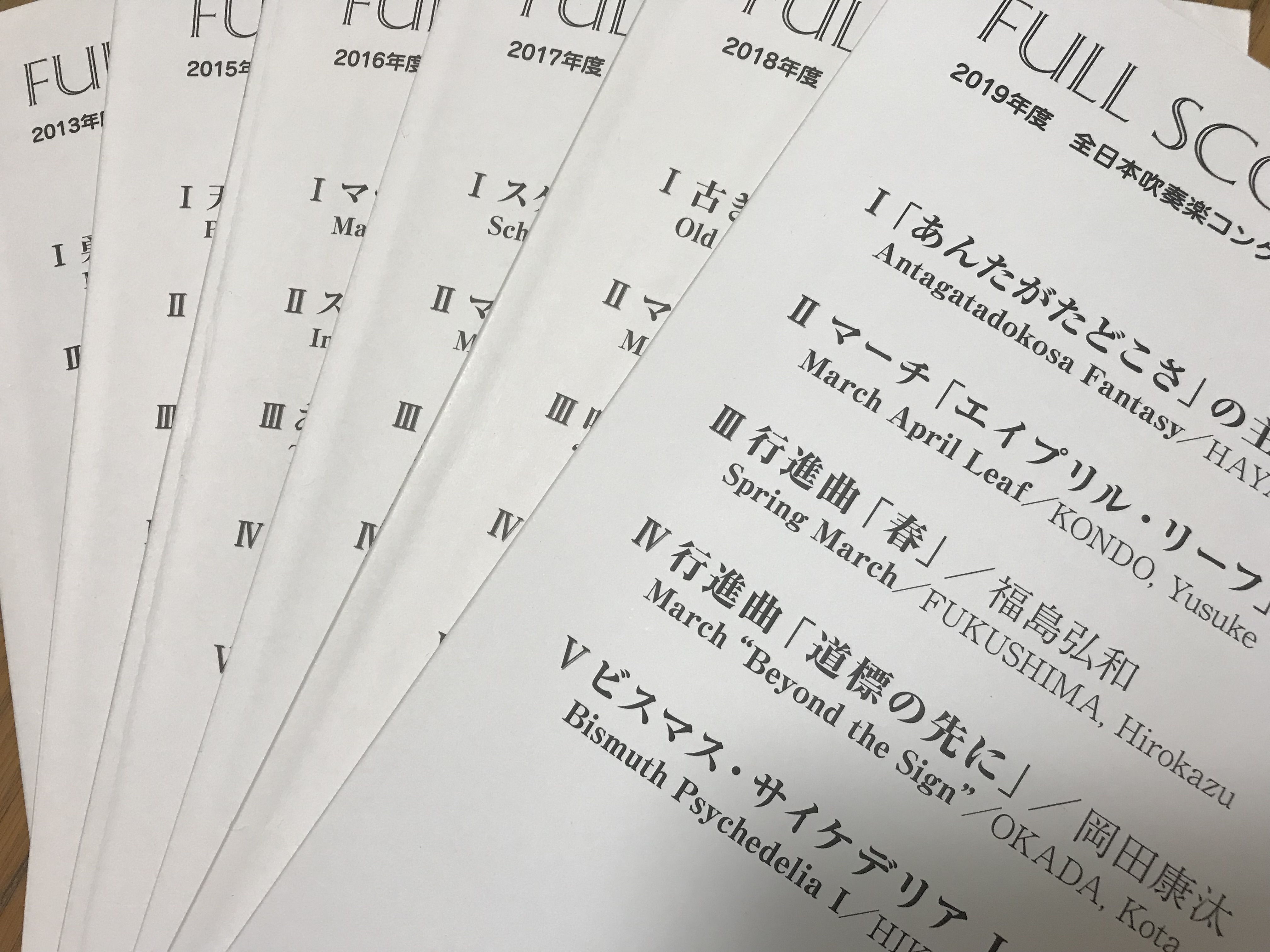
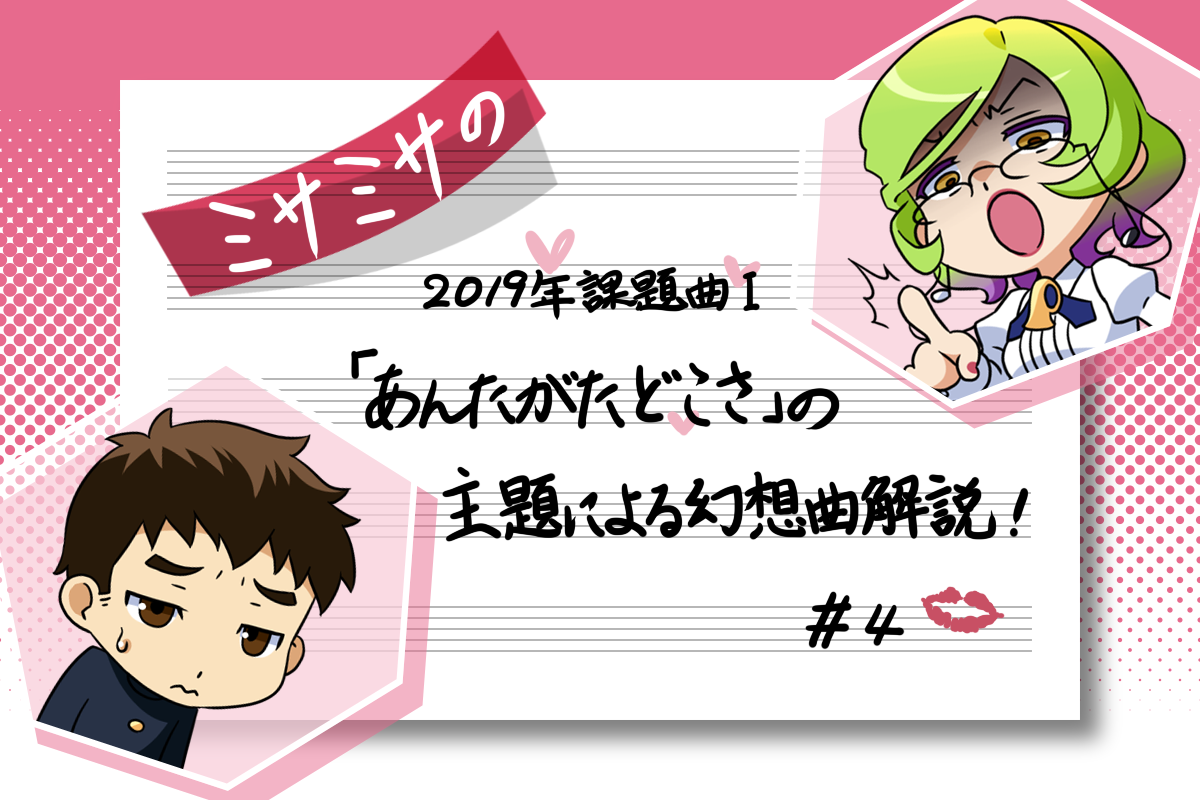
コメント (0件)感想、指摘系はここに。相談は掲示板に。